2021年4月株式会社千葉銀行入行。デジタル改革部兼営業企画部担当部長やデジタル戦略部担当部長を歴任した後、2025年4月より現職。
東京大学医学部卒業後、東京大学大学院医学系研究科医療コミュニケーション学分野助教、大学病院医療情報ネットワーク研究センター副センター長、ダナファーバー/ハーバードがん研究センター客員研究員。著書に『統計学が最強の学問である』(ダイヤモンド社2013)。

千葉大学データサイエンスコア(DSC)では、千葉大学内のデータサイエンス研究者とDXを推進する企業様の連携を通して、データ利活用やAI技術の社会実装を推進しています。今回は、株式会社千葉銀行デジタル戦略部長の伊藤恭子氏を訪問し、データドリブン経営の実践や今後の人材育成のあり方について、DSC西内啓ダイレクターが伺いました。
千葉銀行・伊藤部長:私は2021年に中途で入行しているのですが、その前は新聞社で20年ほどのキャリアを積んでいました。2010年代にHTML5が出てオンラインの記事がリッチになり、ビッグデータとなり、アメリカで普及していたデータジャーナリズムの考え方が日本にも入ってきました。それにより、メディア界も感覚的に訴える記事ではなく、データに基づいてより多くの人に読まれるコンテンツを作成するように変わっていきました。その潮流の中、当時みんなで西内さんのご著書『統計学が最強の学問である』を拝読していましたので、本日はとても楽しみにしておりました!よろしくお願いいたします。
DSC西内ダイレクター(以下「西内D」):そうだったんですね!ありがとうございます。本日はこちらこそよろしくお願いいたします。ちなみに、前職の新聞社から御行へご入行された背景にはどのような思いやビジョンがあったんでしょうか?
伊藤部長:Digital Vortexというレポートがありまして、その中でデジタル技術により破壊されていく業界の順番のようなチャートがありまして、当時メディア、小売、テクノロジー業界というのが最も早く影響を受けるという分析がなされていました。その次の段階で影響を受けるのが金融業という分析であり、私自身が新聞社で紙からデジタル媒体への変化を担ってきた経験が、次に変化が起こる金融業でもお役に立てられるのではないかと思い、入行させていただきました。
西内D:それは素晴らしいですね。そのような流れの中で入行された御行にて行われていらっしゃる、デジタルやAIを使った具体的な取り組みを是非聞かせていただければと思います。
伊藤部長:デジタル戦略部の組織建付けはCoE型です。組織全体として、すべてにおいてデータを大切にし、データをベースにアクションをしようとしています。まずは私たち自身がAIやデータを活用できるよう人材になることで、当行内の業務効率化を加速させることを実践しています。さらにデータ活用を通して当行の行うマーケティング活動や営業活動も高度化していますし、一方で地域の法人のお客さまの業務をAIやデータ活用でサポートさせていただくこともあります。
西内D:なるほど、多方面でデータを活用するための組織づくりをされているんですね。
特に昨今金利のある世界に戻ってきたという大きな環境変化の中で、データ活用周りで課題に感じられている部分はありますか?
伊藤部長:例えば金利のある世界で預金をどのように集めるか?という観点では、営業人員の配置や戦略が今までとは異なります。今後どのようにあると良いか?という『人』のデータを扱う戦略について特に難しさを感じています。
その一方で、ちばぎんアプリのご利用者に対する、預金金利上乗せキャンペーンを行っておりまして(2025年9月現在)、こちらはマーケティングデータを活用しながらお客さまが求める提案ができており、おかげさまでご好評いただいているところです。
西内D:御行のアプリケーションは操作性やデザインの面でとても評判がいいですよね。お客さまへの利便性の向上に大きく投資しており、素晴らしいですね。長期的な視点で考えられている構想や課題は何かありますか?

伊藤部長:次の中期経営計画の注力ポイントとして、汎用的な業務効率化AIや生成AIはかなり精度が良いものが出てきているので、それをそのまま活用しつつ、自分たちに合った形のデータセットが必要な領域については自らチューニングして、効率化や新しい施策を作り出そうとしています。
よくPDCA (Plan ⇒ Do ⇒ Check ⇒ Action) という枠組みでお仕事が語られることがあると思うのですが、PDのフェーズで実施した結果を整理して終わってしまう人が多いことに課題を感じています。その中でCAのフェーズである、分析結果をもとに次のアクションに活かせるメンバーを増やしていきたいと考えています。
西内D:私もPBL (Project Based Learning) を教えることがあるんですが、分析までで終わってしまうのではなくアクションにどのようにつなげるのかという部分にこだわっています。具体的にどのようなアクションがあるかというと実は大きく分けて3つしかありません。①その条件を変えられるか?②その条件を狙えるか?③その条件があっても問題ないように解決させられるか?になります。
例えば私がずいぶん昔に携わった銀行のローン残高と家族構成の関係性の分析では、核家族か?2世帯同居されているか?によってローン残高に大きな違いがあることがわかりました。①その条件を変えられるか?の観点では、基本的に企業から家族構成の変更へのアプローチは難しいと思います。②その条件を狙えるか?の観点では、2世帯同居される家族が参加しやすいイベントは何か?や、いつも見ている媒体は何か?といった点を考慮すると、より効率的なマーケティング施策につながると思います。③その条件があっても問題ないように解決するという観点では、もともと二世帯同居という条件があったとしても借りやすい銀行ローンとはどんなものか?と考えだしてみるという方法です。
伊藤部長:西内さんのおっしゃる施策につなげるためのアイデアを導くアプローチは、非常に重要ですね。今の学生の皆さんはPBLが当たり前になってきていますが、働き盛りの世代はPBLを学生時代に経験していない世代なので、業務や研修を通して身につけていく必要があるスキルだと思います。
それともう一つ西内さんに聞いてみたかった部分ですが、今後更に会社全体として統計学や分析に関する力を伸ばし、底上げしてきたいと考えていますが、どのような部分を伸ばしていくとよいでしょうか?
西内D:様々な企業様のデータ活用をお手伝いしてきた中で、実際のビジネス現場で生きる統計リテラシーは大きく分けて3つあると思います。
① なんとなくデータで差があるように見える場合に、それがたまたまの誤差ではなく再現性のある差なのか?という点をP値や信頼区間で確認をすること
② 2つのグループを比較しようとしたときに、その要素以外の要素で偏りがない比較ができているのか?ということを業務・業界知識をもとに確認すること
③ データサンプルがとられている集団がアクションをしたい現実の集団と差異がないか?という確認
データを活用した事業では上記3つの観点を持ちながら推進していただけるとよいと思います。
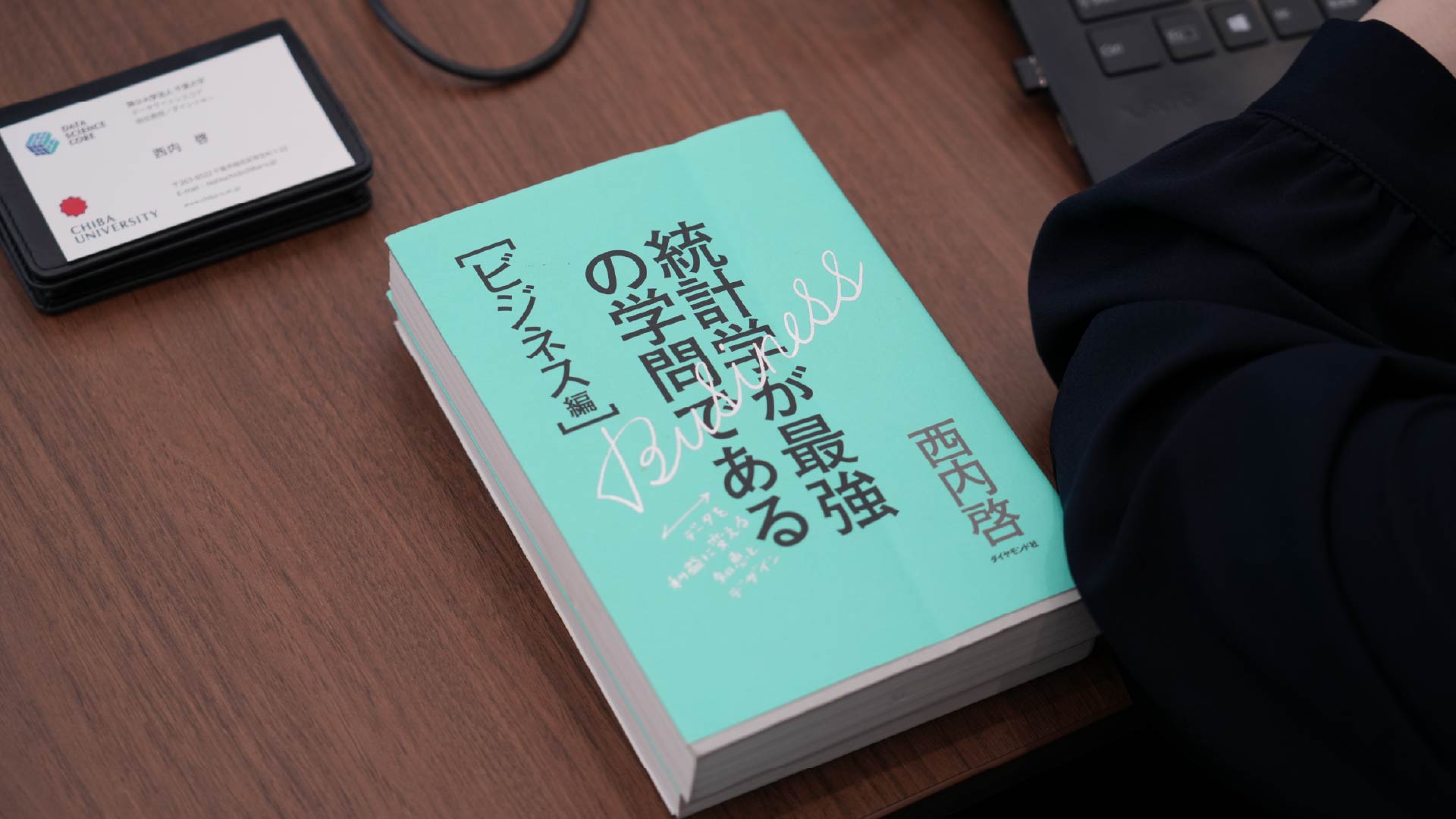
伊藤部長:ありがとうございます。これからまさに当行内でもより多くのメンバーが実践を通しながら身につけていく必要がある能力だと思います。
西内D:最後にこの記事を見ていらっしゃる様々な方に向けてメッセージをおねがいします。
伊藤部長:私が当行に入社して感じたことなのですが、銀行は個人/法人ともに本当に膨大で様々な種類のデータがあり、まさにデータの宝庫だなと感じています。今まではこれらの情報を大切にお預かりして保存しておくだけでした。これからもデータを大切にお預かりすることは変わらずですが、それに加えて分析で得られた知見をもとにそれぞれのお客さまに合った適切なご提案や価値のご提供ができるようになります。そういった意味でデータ活用が進むことにより、お客さまにはより便利でご要望に合わせたご提案をスピーディに実施させて頂きたいと思います。また今後中途・新卒問わず当行への入社を検討されている方については、データを活用して実社会に大きく影響を与えるフィールドが広がっていることが一つの魅力になるのではないかと思います。一緒にデータを活用して、社会全体をより便利にしていただける方の挑戦を心よりお待ちしています。
西内D:今後の御行の更なるデータ活用推進がとても楽しみです。
本日は貴重なお話を頂きまして、誠にありがとうございました。